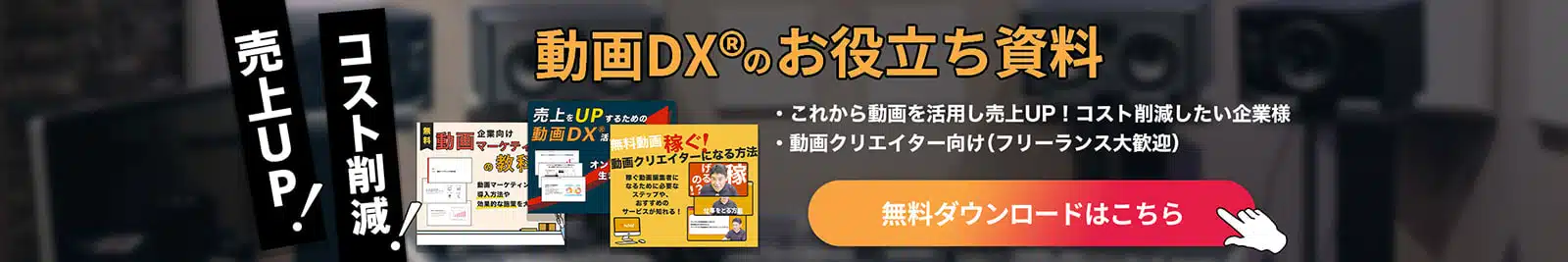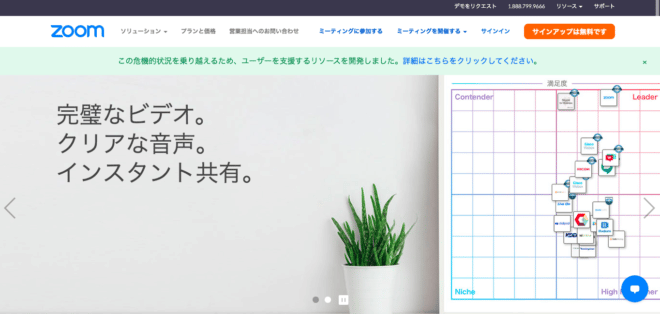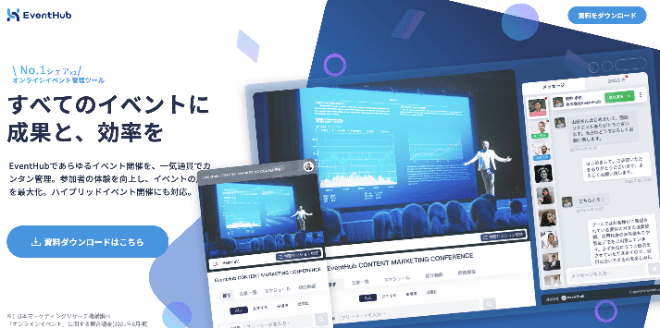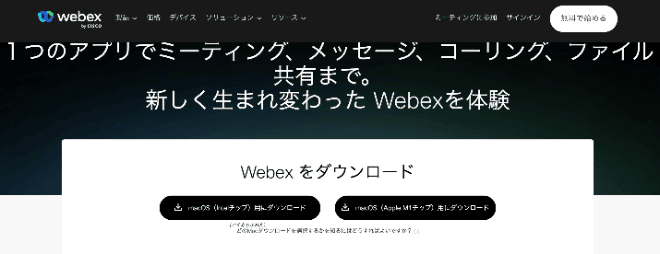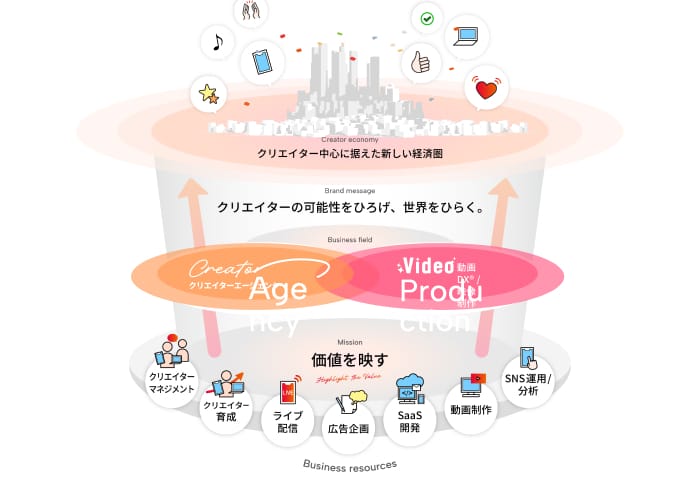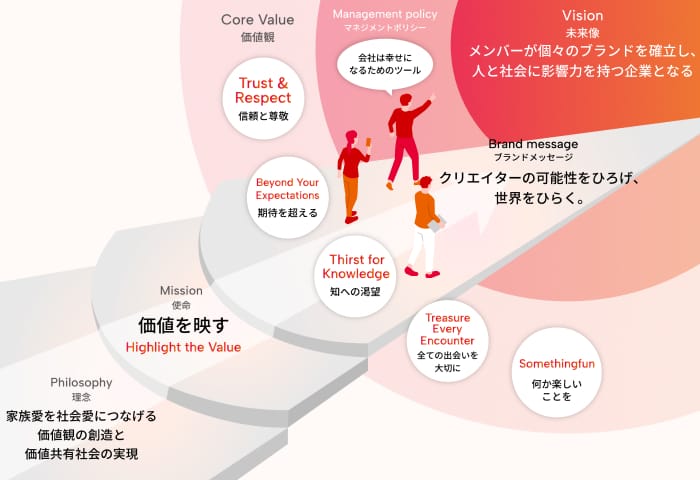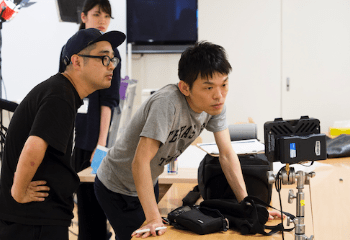皆さんは、ウェビナーという言葉を聞いたことがありますか?
最近は新型コロナウイルスの影響で、対面でのセミナー開催が難しくなっているため、Webで開催するセミナー「ウェビナー」が普及しつつあります。
このページでは、そんなウェビナーについてメリット・デメリット、これからウェビナーを始める方に向けたおすすめのツールも紹介していきます。
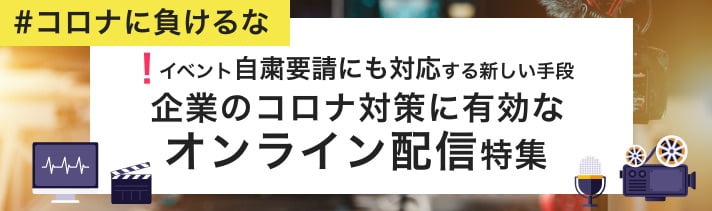
目次
ウェビナー(Webセミナー)の基礎知識

これまでセミナー、会議、就職説明会、面接は人と人がオフライン(対面)で行うのが普通でした。
しかしインターネットの発達や新型コロナウイルスの影響により、昨今はウェビナー形式での開催が普及しつつあります。
ウェビナーであれば、参加者はインターネット環境さえあれば、パソコンやモバイルを使ってどこからでも参加することができるからです。
その手軽さから、最近では積極的にウェビナーを活用する企業も増えています。
ウェビナーの種類を紹介

まず、どのような種類のウェビナーがあるのかを見ていきましょう。
リアルタイム配信or録画配信
「リアルタイム配信」とは、主催者と参加者が同時刻に開催/参加する形式です。
「ライブ配信」と呼ばれることもあります。
それに対し、「録画配信」は、主催者が事前作成しておいた録画を配信する形式です。
リアルタイム配信の場合、主催者は参加者とリアルタイムでコミュニケーションを取ることができます。
一方、録画配信は参加者が時間・場所を問わず視聴できるので、学習系コンテンツや採用現場でも採用されています。
一方向配信or双方向配信
リアルタイム配信は、さらに2種類に分けることができます。
ひとつは、主催者側が主導権を握り、コンテンツを一方的に流していく「一方的配信」。
もうひとつは、参加者からの質問や意見などを拾いながら対話式で進行する「双方向配信」です。
双方向配信の場合、チャット機能などもうまく活用することで、ウェビナーの臨場感やコンテンツの信頼性を高める効果も期待できます。
会場セミナーと比較したウェビナーのメリット

しかし、新型コロナウイルスの影響もあり、従来は当たり前だったことが難しくなりつつあります。
この章では、従来の会場に集まって行うセミナーと、オンライン上で行うウェビナーを比較しながらウェビナーのメリットをご紹介します。
コストが掛からない
主催者側と参加者側の両方にとってメリットになるのが、これまで発生していた費用がかからないということです。
ウェビナーの場合は、主催者がイベントスペースや大掛かりな機材を借りる必要がありません。
そのため、設営や撤去費用などのコストを大幅に削減することが可能です。
遠方に住んでいる参加者にとっても、ウェビナーであれば、自宅などから気軽に参加することができるので嬉しい節約にもなりますね。
場所に縛られない
開催者と参加者が、場所を問わずセミナー開催/参加できる点も、ウェビナーの大きなメリットです。
会場を借りてイベントを開催する場合は、主催者がレンタルスペースの担当者と、会場やスケジュールの調整を行う必要があります。
知名度が高い人気会場だと、他のイベントとバッティングして理想の日程を抑えられなかったり、想定している収容人数・予算に見合う会場が見つからなかったりする場合もあります。
一方、オンラインで開催するウェビナーの場合は、開催会場や参加者の収容人数を考慮する必要がないため、日時も場所も会場に縛られることがありません。
好きな時間に視聴できる
ウェビナーを録画型の配信にすると、参加者は好きな時間に視聴することができます
これまでは、就職活動などの企業説明会では学生が会社を直接訪れるのが一般的でした。
しかしウェビナーを導入すれば、企業は事前に制作しておいた事業説明動画をオンライン上で公開する、といった対応ができます。
対面開催だと都合がつかない参加者でも、録画型であれば参加できるのでより多くの参加者へリーチすることができます。
コンテンツを理解しやすい
ウェビナーでは、画面共有や資料アップロードも可能です。
参加者はパソコンやスマートフォンで資料を閲覧しながらウェビナーに参加することで、コンテンツへの理解度を深めることができます。
主催者と参加者が対話できる双方向配信の場合は、チャット機能を活用することで、参加者の質問にリアルタイムで解答することもできます。
ウェビナー配信ツールを選ぶときのポイント

この章では、数あるウェビナーツールの中から、ご自身にぴったりのツールを選ぶためのポイントを解説します。
参加者は何人分まで対応しているか
あなたが行おうとしているセミナーは、何人の参加者を想定していますか?
ウェビナーによっては「無料で◯人まで使えるが、それ以上の参加者に配信する場合は有料版」など、参加可能人数に応じて料金・プランを変えているサービスがあります。
例えば企業の説明会など、多くの参加者を募りたい場合は50人〜100人のキャパシティがあるサービスを選ぶようにしましょう。
資料共有がスムーズかどうか
ウェビナーに参加した顧客満足度を左右するのが、資料です。
ウェビナーのサービスを選ぶ際は、資料共有の方法を確認しましょう。
資料のアップロード、主催者の画面共有など、資料の共有方法にも様々なバリエーションがあるからです。
録音&録画機能の有無
ウェビナーに録音・録画機能がついているかどうかを確認しましょう。
ウェビナーの様子を録画することができれば、参加できなかった人にも別途共有することができます。
参加者も後日再視聴することができれば、コンテンツへの理解度も一層深まり、満足度を更に高めることができるでしょう。
チャット機能の充実度
対話を重視したいウェビナーでは、チャット機能は必須と言えます。
参加者が多いウェビナーだと発言しづらい、という参加者も少なくないからです。
インターネット環境が不安定な参加者もいることを想定し、チャット機能は常に使えるようにしておきましょう。
例えば語学学習系のウェビナーであれば、音声だけでなくチャット機能も使ってあげると、参加者はスムーズに理解できます。
無料体験版の有無
使ってみたいと思うウェビナーを見つけたら、まずは無料体験版を使ってみることをオススメします。
インターネット接続は問題なかったか、チャットはスムーズに使えたか、資料や画面の共有はできたか等、ご自身がウェビナーを開催する上で必要な手順・機能を確かめてください。
また、主催者が使いやすいと思っていても、参加者にとっては使いにくかったというケースも十分考えられます。
初回のウェビナー開催後、参加者からもフィードバックをもらいましょう。
オススメのウェビナーツール10選

ここからは、具体的におすすめしたいウェビナーツールを紹介していきます。
ウェビナーツール1. Zoom Webinar
「Zoom飲み」という造語ができるほど一般的に普及しているZoomです。
Facebook ライブや YouTube ライブと連携して配信することができる点が特徴です。
画面はパネリスト(画面に登場する人)と視聴者の2つに分けられます。
視聴者が何らかのアクションを起こしたい場合は「チャット」「手を挙げる」「Q&A」の3つ。
「Zoom ミーティング」と比較して、「Zoom webinar」は、よりセミナー向けに特化して作られたサービスと言えるでしょう。
ウェビナーツール2. WebinarNinja
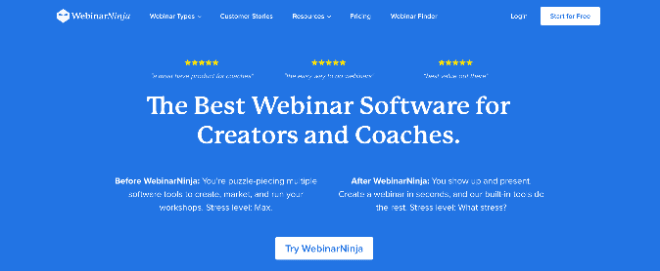
Web セミナーやオンライン会議をする上で必要な機能が揃っている、オールインワンのツールです。
29ドルの基本プランでは、最大50人のライブ参加者が許可されますので、小規模から中規模程度のウェビナーをやってみたいという方におすすめです。
統計情報やフォローアップメールなどによって、収益化に向けて改善していくこともできるでしょう。
ウェビナーツール3. LiveOn
LiveOnは、完全自社開発型の製品であり、音声遅延と音切れを防ぐための独自技術を採用しています。
海外の拠点や、大人数での参加により通信環境に負荷がかかる場合であっても、ストレスのないクリアな音声を実現しています。
Microsoft各種を共有できる「資料共有機能」をはじめ、ホワイトボード、録音機能、メディア再生など様々な機能を使用可能です。
日本語以外にも、中国語と英語に対応しているので、海外クライアントとの会議でも安心して利用できますよ。
ウェビナーツール4.V-CUBE セミナー
V-CUBE セミナーは、最大26,000箇所での同時接続や、PC・スマホ・タブレットなどの様々な機器で安定した配信環境での配信が可能です。
また、ウェビナーの開催が初めてで必要機材や進め方がわからなくても配信のプロのサポートを受けられるので安心して配信ができます。
他にもウェビナーを開催する上であると嬉しいチャット機能やセミナー申し込みフォーム作成機能などの機能も豊富です。
ウェビナーツール5.Event Hub
Event Hubは、アプリのインストールが不要で、管理画面がシンプルでわかりやすいので、初心者におすすめのツールです。
管理画面はシンプルですが機能が少ないわけではなく、他のウェビナーツールにもあるような視聴データの記録やアンケート、登録フォームなどの便利機能も豊富で、ウェビナー以外の様々な配信イベントにも対応しています。
ウェビナーツール6.Cisco Webex
Cisco Webexは、インストールが必要な有料ツールですが、無料で使えるプランもあります。
また、インターネット機器で有名なCiscoのツールなので、互換性の良い専用のデバイスも販売しています。
有料プランで契約すれば様々なサポートも受けられますので、わからない部分を聞きながらウェビナーを開催するということもできるでしょう。
ウェビナーツール7.LOGOSWARE GigaCast
LOGOSWARE GigaCastは、ウェビナー配信専用システムです。
他のツールはウェビナー以外にも様々な配信イベントができるものもありますが、LOGOSWARE GigaCastは本格的なウェビナー向きなので、ウェビナーに必要な機能が十分に揃ったツールです。
機能が多すぎてわかりづらいということがなく、配信方法も、ライブ配信、セミナー録画、オンデマンド配信に対応しています。
また、無料でテスト配信ができるので、どのように配信をするのかが実際に体験できます。
ウェビナーツール8.FreshVoice
FreshVoiceは、日常の会議からウェビナーまで幅広く活用できるツールです。
タイプの異なる5つの製品があるので、目的に応じた製品を活用するのが良いでしょう。
また、どれを使ったら良いかわからなくても無料トライアル版があるので、無料で体験してみてから決められますし、使い方に合わせてカスタマイズしてくれるサービスもあるので様々な使い方に合わせられます。
ウェビナーツール9.Cocripo
Cocripoは簡単にウェビナーを行えることに特化しています。
管理画面が簡単なだけでなく、参加者もURLをクリックするだけで、顔出しもないので簡単に参加できるようになっているのです。
また、初めて有料プランを利用する場合、1ヶ月無料で利用できるので、使用感がわかりやすいのも特徴です。
ウェビナーツール10.Adobe Connect
Adobe Connectは、リモートワークの際の会議や、イーラーニング、ウェビナーなど、様々な使い方ができます。
配信時の遅延がなく、様々な方法での画面共有ができるなど、機能も豊富で幅広い使い方できるツールです。
30日間の無料体験版もありますので、まずは体験版を利用してみるのが良いでしょう。
おわりに:ウェビナーツールを積極的に活用しよう

ウェビナーは非対面のため、参加者の雰囲気がわかりにくいというデメリットもありますが、チャット機能などをうまく使って、参加者から積極的な発言を促す工夫もできます。
ウェビナーは場所や時間にとらわれず開催でき、コストも削減できるため、これからの時代において積極的に取り入れて行きたいツールです。
このページを参考にしていただき、社内会議やセミナー、採用活動をウェビナーで開催してみてはいかがでしょうか。