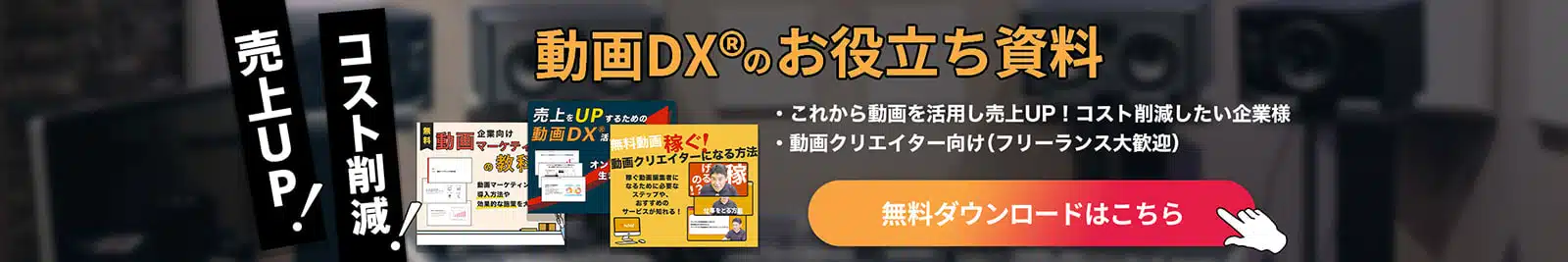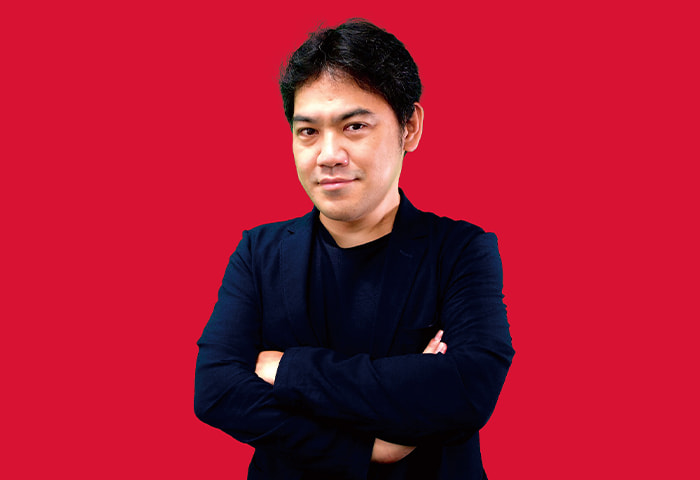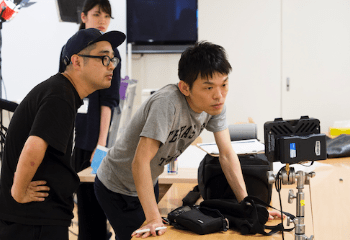コロナ禍でリモートワークの導入が加速し、会議や授業、そしてセミナーもオンラインで動画配信される機会が飛躍的に増えました。
しかし初心者は、いざセミナーを動画で配信しようと思っても、何からどう始めていいか、なかなかイメージが湧かないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、セミナーを企画し動画配信するまでの流れと、オンラインセミナーのメリット、そしてセミナー動画作成の注意点を、初心者にもわかりやすく解説します。
ぜひ参考にしてみてください!
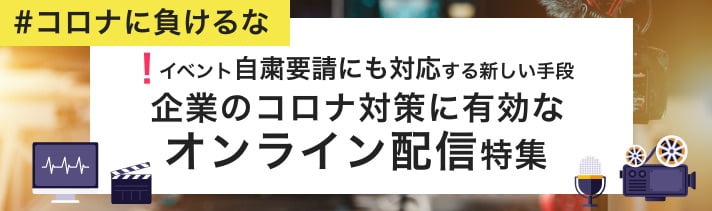
目次
セミナーを動画で配信する流れ

まず、セミナーを動画で配信するための8つのステップを解説します。
ステップ1.セミナーの内容を企画する
企画はすでに大まかに決まっていると思いますが、動画で配信するにあたって改めて言語化しておくと後の工程がスムーズになります。
具体的には、
- 目的(セミナーの実施によって目指すゴール)
- ターゲット(誰に見てもらいたいか)
の2つを言語化しましょう。
この2つが明確になると、企画の詳細部分も自ずと決まってきます。
たとえば、
目的:資産運用セミナーを通して新規顧客を獲得したい
ターゲット:資産運用に関心を持つ30代〜60代
といったかたちで言語化してみてください。
そのうえで、ターゲット層が一番見やすい日時・長さ・見せ方は何かを検討しましょう。
目的とターゲットから企画を検討していくことで、より適切な動画の内容と配信方法を導き出せます。
逆に、目的とターゲットが曖昧なまま動画の体裁を決めてしまうと、それがターゲット層にそぐわず、結局ほとんど見てもらえないという失敗につながりかねません。
ステップ2.配信の種類を決める
セミナーの動画配信には、大きく3つの種類があります。
【オンデマンド配信】
事前に収録しておいたセミナーの動画を配信する方法です。
あらかじめ動画を編集できるため、補足説明や視覚効果を足して動画のクオリティーを上げることができます。
また、1回のセミナーに限らず、何度でも使いまわせる持続的なコンテンツにもなり得ます。
【完全ライブ配信】
セミナーの様子をリアルタイムで撮影し動画配信する方法です。
ライブならではの臨場感が出せるほか、チャット機能で参加者の反応を知りながら内容を臨機応変に調整することができます。
【擬似ライブ配信】
オンデマンド配信と完全ライブ配信の中間にあたる方法が擬似ライブ配信です。セミナーの動画自体は事前に収録したものを配信し、チャットなど参加者とのコミュニケーション部分だけリアルタイムで行います。
それぞれの特徴を踏まえて、自分のセミナーに最も適切と思われる方法を選びましょう。
その際、以下のメリット・デメリット表を参考にしてみてください。
| メリット | デメリット | |
| オンデマンド配信 |
・作成動画のクオリティーを上げられる |
・動画作成の手間が大きい ・参加者の反応にあわせて調整ができない ・臨場感が薄い |
| 完全ライブ配信 | ・臨場感が出て聴衆のモチベーションが上がる ・参加者の反応にあわせて内容を臨機応変に調整できる |
・一発勝負でやり直しがきかない ・動画そのものに視覚的なインパクトが出しづらい ・参加者の参加日時が限定される |
| 擬似ライブ配信 | 完全ライブ配信のリスクなく参加者とリアルタイムのコミュニケーションがとれる | 完全ライブ配信ほどの臨機応変さは担保できない |
ステップ3.配信の環境を決める
セミナーの動画を配信するにあたって、以下2種類のうちどちらかの環境を選ぶ必要があります。
【オープン環境】
特に制限を設けず、不特定多数の人が自由に見られるタイプの配信環境です。
できるだけたくさんの人に参加してもらいたい場合に向いています。
【クローズド環境】
参加に条件を設定し、パスワードなどを配布して特定の人だけが見られるタイプの配信環境です。
有料セミナーや、一般公開したくない情報を扱う場合、限定感を演出したい場合などに向いています。
自分のセミナーにより適していると思われる方を選びましょう。
ステップ4.配信のツールを決める
オンデマンド配信ではセミナーの動画データを参加者に共有するだけでも実行可能ですが、ライブ配信や擬似ライブ配信の場合は専用ツールの利用が必須です。
初心者に特におすすめなのは、以下の5つのツールです。
チャット機能の有無、定員数、費用などを確認したうえで、自分のセミナーに最適と思われるものを選びましょう。
こちらのページに各ツールの特徴をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
ステップ5.セミナーを撮影する
セミナーの内容によって異なりますが、動画撮影にあたって最低限必要なものはおおむね以下の通りです。
<機材>
- ビデオカメラ
- 三脚
- マイク
<人員>
- スピーカー
- カメラマン
カメラを2つ以上にしてカットの種類を増やしたり、プロのカメラマンに依頼したりすることで、動画のクオリティーがより向上します。
特にオンデマンド配信または擬似ライブ配信の場合は、撮影後に動画を編集できるため、セミナーを一発撮りする必要がありません。
あらかじめ台本とカット割を作成し、そこにあわせて何度も区切りながら撮影するといったことも可能です。
撮影にかかる手間とコストが大きくなりますが、その分動画のクオリティーが上がり、参加者の満足度も向上します。
一方、完全ライブ配信の場合は、撮影と同時に配信も行う必要があります。
複数のアングルを切り替えるなど、見栄えの凝ったの動画をつくることはやや難しくなります。
編集ができない分、セミナーでは説明ボードなど視覚要素を使って、参加者にわかりやすいよう工夫することが大切です。
完全ライブでもできるだけ凝った動画を配信したい場合は、セミナーのライブ配信に実績のあるプロの製作会社に依頼するのがおすすめです。
サムシングファンのライブ配信サービス詳細はこちら
ステップ6.撮影動画を編集する
撮影動画をそのまま配信することも可能ですが、オンデマンド配信や擬似ライブ配信の場合は、編集によってよりわかりやすく、インパクトのある動画に仕上げることができます。
具体的には、以下の点を工夫して編集するのがおすすめです。
- 字幕をつけて内容を参加者により印象付ける
- 不要な部分をこまめにカットし、テンポ感を出して参加者を飽きさせない
- できるだけ雑音をカットし、一方で適宜効果音をつけて聞きやすくする
- 説明がわかりにくい部分には補足説明や画像を追加する
動画作成のコツはこちらの記事でも詳しく解説しています。
ステップ7.撮影動画を配信する
配信にあたっては、ツールの手順をあらかじめしっかりと確認し、当日アクシデントが起こるリスクをできるだけ減らしておきましょう。
また、可能であれば事前に配信テストを行っておくことをおすすめします。
完全ライブ配信や擬似ライブ配信の場合は、チャット機能もシミュレーションしておくとよいでしょう。
実際にやってみることで、必要な準備や足りていない人員などが明確になり、当日の配信がよりスムーズに行えます。
ステップ8.効果測定をする
配信終了をもってプロジェクト終了としてしまってもよいのですが、最後にセミナーの動画配信でどんな効果が得られたかをしっかり分析しておくと、次回のセミナー企画や今後のマーケティング戦略に生かすことができます。
たとえば、実際のセミナーでも行う参加者アンケートは、動画配信でも実施することができます。
配信ツールのなかには、LiveOnなどアンケート機能があらかじめ備わっているものや、CRMツールと連携して詳細にユーザー分析ができるものもあります。
また、オンラインセミナーの場合、実際のセミナーではなかなか見えないようなデータも得られます。
たとえば、セミナーのどの時間帯に最もアクセスが集まったか、どの項目で最もチャットが盛り上がったかなども、今後の施策を検討するうえでの貴重な情報になります。
セミナー動画におすすめの動画制作会社3選

ここからは、セミナー動画の制作を依頼するのにおすすめの動画制作会社を3社厳選して紹介していきます。
今回紹介する動画制作会社は、
- 株式会社サムシングファン
- 株式会社フォー・ファイヴ
- 株式会社ナツメスタジオワークス
の3社です。
それぞれ詳しく紹介していきます。
おすすめ1. 株式会社サムシングファン
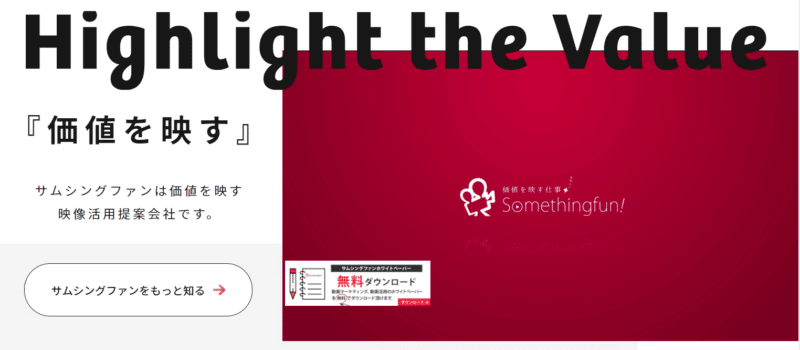
引用:株式会社サムシングファン
株式会社サムシングファンはセミナー動画を含む映像制作で有名な動画制作会社です。
主な特徴としては以下の3点があげられます。
- 映像制作の実績が豊富
- セミナー動画の制作も依頼できる
- ライブ配信も依頼できる
注目なのが、ライブ配信も依頼できるという点です。
需要が高まってきているオンラインセミナーの実施もサポートしてもらえます。
おすすめ2. 株式会社フォー・ファイヴ

引用:株式会社フォー・ファイヴ
動画制作をメインにおこなっている広告制作会社、株式会社フォー・ファイヴ。
株式会社フォー・ファイヴの主な特徴としては、以下の3点があげられます。
- セミナー動画の実績が豊富
- 料金がシンプルでわかりやすい
- オプションが豊富
株式会社フォー・ファイヴでは、「すぐトル」というセミナー動画制作サービスが用意されていて、初めて撮影する方でも安心して撮影できるよう徹底的にサポートしながら撮影をおこなってくれます。
おすすめ3. 株式会社ナツメスタジオワークス

「セミナー制作.com」というセミナー動画専用の制作サービスを提供している、株式会社ナツメスタジオワークス。
株式会社ナツメスタジオワークスの主な特徴としては、以下の3点があげられます。
- セミナー動画の制作に特化したサービスを提供している
- 10,000以上のセミナー動画の制作実績がある
- セミナー動画専用のスタジオを所有している
株式会社ナツメスタジオワークスは創業13年で制作実績10,000以上と申し分ないほどの実績がある制作会社ですので、セミナー動画の制作を安心して任せることができます。
セミナー動画を配信するメリット

セミナーを動画で配信するメリットについて紹介していきます。
メリット1:コストを大幅に削減できる
セミナーの規模にもよりますが、実際のセミナーの費用と比較すると、会場レンタルや参加者への物理的な接待がなくなる分、動画配信の方がコストを大幅に削減できます。
メリット2:場所・天候・交通事情の影響を受けない
どこからでも参加できるため、日本全国、さらには世界各国から集客が可能です。
天候や交通事情にも影響されず、交通費も発生しないため、参加のハードルも格段に下がります。
オンデマンド配信の場合は、日時の制約も外すことができます。
メリット3:双方向コミュニケーションが活性化する
実際のセミナーの場合、大人数を相手にするほどコミュニケーションが「スピーカー→参加者」の一方通行になりがちです。
しかし、オンラインなら比較的質問が投げかけやすく、チャット機能でより密で活発なコミュニケーションが取れるようになります。
メリット4:実施のハードルが低い
セミナー動画は動画編集の手間はかかりますが、会場手配や資料の増産、参加者への接待など物理的な準備が必要なくなる分、実施のハードルが格段に下がります。
セミナー動画を作成する際の注意点

セミナー動画を制作する際、注意しなくてはいけないのが、
- わかりやすい動画を作る
- 聞き取りやすさにこだわる
- 見やすさにこだわる
の、3点です。
それぞれ詳しく解説していきます。
注意点1. わかりやすい動画を作る
セミナー動画は視聴者に知識やノウハウを伝えるための動画です。
そのため、視聴者が知識やノウハウを自分のものにできるほどわかりやすい動画である必要があります。
あまり内容を詰め込みすぎず、テンポの良さを意識した動画作りを意識しましょう。
自分がわかりやすいと感じるセミナー動画を参考にするのもおすすめですよ。
注意点2. 聞き取りやすさにこだわる
いくらわかりやすい動画を作っても音声が聞き取りにくいようでは意味がありません。
セミナー動画はその他の動画以上に音声の聞き取りやすさが重要になるため、マイクや録音環境にこだわり、聞き取りやすさを意識しながら動画を制作するようにしましょう。
注意点3. 見やすさにこだわる
セミナー動画では、音声と同じくらい画質の鮮明さ、見やすさにもこだわらなくてはいけません。
セミナー動画ではホワイトボードやプロジェクターを活用するかと思いますが、それらに書かれている内容がボケて視認できないようでは意味がありません。
必要な情報を視聴者がしっかりと視認できるよう、見やすさにもこだわるようにしましょう。
こちらの記事も参考にどうぞ!
まとめ:流れを把握してセミナーの動画配信を成功させよう!

配信ツールもどんどん充実し、今やセミナーの動画配信は誰でも簡単に実施できるようになりました。
しかし、全体の流れを把握しないままなんとなく始めてしまうと、肝心のターゲット層に届かなかったり、効果がいまいち実感できないまま終わってしまったりすることもあり得ます。
全体像をしっかり掴み、十分に準備をしたうえで、初めてのセミナー動画配信を成功に導いてください!